-研究室紹介-
教育の目指すところ
大学教育に求められていることは,知識・情報を学生にタタキ込むということではなく,大学入学時での「言われたことをやっていれば誉められる」という受動的な学習姿勢を,未知の問題に挑戦するという活力ある能動的学習姿勢へと転換することについるのではないかと考える. しかしこれは,教室における従来型の教育で対応することは不可能であるといっても過言ではないと思われる.教員を中心とする研究室における「寺子屋」式教育によって解決することの他には,良き方策は見当たらないと筆者は考えている.そこで,ゼミナールでは,文献を読むという従来型のゼミナール形式では,学生諸君の受動的学習を打破することは困難と考え,毎回一つの課題を提示し,この課題を学生諸君の今までに学習してきた財産(?)である基礎知識を活用して解決するプロセスを身に付けさせることを主眼にトレーニングを行っている.初期の段階では,質問の意味を理解し,的確に自分の考えをまとめて発表するトレーニングに主力がそそがれることになります.そして,次のステップでは今までの学習をもとに問題を解決するプロセスを習得することに多くの時間を費やすことになるわけです. ここで、本年度のゼミナールでの3年生の感想の一部を紹介します.「ゼミを受けてきて今思うのは,大学に入ってはじめての授業らしい授業だったということだ.今まで受けてきた他の講義のような,先生から学生への一方通行の知識の伝達ではなく,きちんと学生の理解度や考え方が先生にフィードバックされて授業が進められていく.そのおかげで授業中も緊張感を持つことができ,充実した時間をおくることができた.正直にいうと,最初の頃は,その緊張感に耐え難い気持ちもあったと思う.授業のたびに自分の頭の中がいかにさびついているかという事実を,また大学に入学してからいかに自分の吸収できた知識が少ないかという事実をつきつけられる感じがじて・・・」. 4年生になると,卒業論文研究という能動的学習に取り込むことになります.そして,当研究室の研究テーマは原則として卒業論文研究さらには修士論文のテーマとして,現在次の分野を取り上げているところです. (1)エネルギー動力システムのダイナミクスと制御ならびに最適設計に関する研究(新しい高効率エネルギーシステムに関する研究) (2)熱システムの性能向上(高性能伝熱管の特性評価・開発等々) (3)空気圧システムの特性評価 なお,これらのテーマは,エネルギーの有効活用を中心に地球環境問題の一つの解決を目指した実験研究として展開しているものであります. 以上で述べたように,現在の大学教育(少なくとも学部教育については)に求められていることは,”○○工学”に関する専門教育ではなく,工学問題に取り組む能動的な基本姿勢の確立と将来の未知の工学問題に取り組むための工学の基礎的な知識の習得であるということに要約されると考えます.したがって,研究室を中心とする教育研究の位置づけは,能動的な基本姿勢を確立するためのプロセスを学習する”場づくり”ということになるわけです.21世紀にはもはや各個別工学が主役を演ずる時代ではなく,人類の世界的規模の課題に総合的あるいは学際的に挑戦することが求められることから,この”場”での人材育成が最も大切な大学の役割と考えられます.このため,この”場作り”に最も大きな重点をおきつつ,当研究室の活動が展開されているところであります. |
||
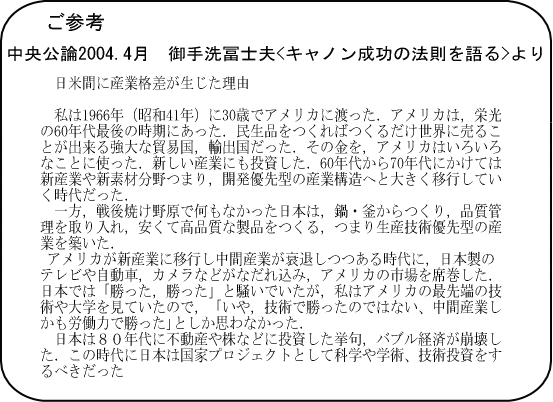 |
||
| Copyright(C) KAWAI LABORATORY 2005 All rights reserved. |